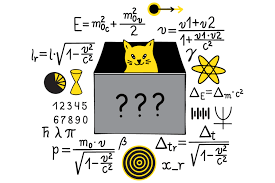幻夢の自己相似構造(フラクタルドリームスケープ)
小説家YUMI 坂口由美
序章 ― フラクタル迷宮の目覚め ―
人は、「自分が信じている世界」が本当に存在しているのかと疑ったことがあるのだ。
18歳のレンは、夜ごと無限に枝分かれする螺旋階段の夢を繰り返し見ていた。
日常の出来事や読んだばかりの小説が、時空を超えてふわりと今日の現実にさざ波のように響いている。都市のビル群、通学路の木立すら、夢で見るフラクタルな「仮想現実」に重なって感じられた。
「世界が自己似たフラクタル構造で編まれた仮想現実だったら、認識や偶然――そんな当然すらいで揺らぎそうね。」
蒼井教授の問いかけに、レンは戸惑いながらも聞きます。
「量子テレポーテーションを知っているかい? 情報としての現実が、異なる場所へと転写される。これは物理現象だけど、世界の本質や記憶、存在の境界の彼方、この謎が照らしてくれて気がしたんだ。」
世界のどこまでが「本物」で、どこからが夢なのか。
レンは次第に、毎日目にするものすべてに疑念を抱き始めます。
現実と夢、自分と他人、時間と空間――すべての境界が、フラクタル模様のように複雑になり乱れていく。
彼は「本当の世界」の姿を求めて、一歩を踏み出す。
宇宙として見えているもの=深層意識の奥深い投影
第一章 ― 深層意識の宇宙 ―
夕焼けが差し込む慶応義塾大学の科学室。窓辺でレンは覗いている。
「教授……今、世界が見ている宇宙も、実は“現実”じゃないんですか?」
蒼井はゆったりとうなずき、ホワイトボードに円を描く。
「古典物理学は客観的な宇宙を前提とした。だが、量子論では観測者の『意識』が現象を思い切って決めてしまったのだ。」
「意識が、現実を守っているのですか?」
微笑んだ蒼井は続く。
「……美しい、って思うんだ。科学も、哲学も、心も、全部つながって“本当の現実”を見せてくれる気がする。」
「現実の扉を開く鍵は、君の好奇心と挑戦心だよ。」
その夜、二人の静かな対話から、新しい世界の幕がひっそりと現れた。
「箱の中の奇妙な現実」――シュレーディンガーの猫
第二章 ― 箱の中の不思議な現実 ―
シュレーディンガーの猫と量子世界のパラドックス
レンは夕焼けに染まる研究室で挑む。
「教授、本当に猫は『生きていながら、死んでもいるのですか?」
「それがシュレーディンガーの猫の不可思議さ。観測されるまでは、猫は生と死の両方が重なって存在する。」
「現実じゃ考えられないのに――。」
「この中に猫がいると想像してみよう。君が観測者になることで、重ねられた『現実』がひとつに定まる。」
「僕が見なければ結果は決まらない…?」
「そうだ。でもマクロな世界――自己同様に広がる現実では、私達的に最終一つの状態しか観測できない。それが量子の奇妙。」
レンはそっと箱を見つめた。 「僕も、まだ未知の可能性をたくさん抱えているってことですね。」
箱の中では、猫が生きているかもしれないし、死んでいるかもしれない。
現実と可能性が交差するその静かなひととき――彼らは自分自身の中にも重なった無数の可能性を見ていた。
変わる過去と相対する――タイムマシンと沈黙する宇宙
第三章 ― 時を越えるカケラ ―
―存在と「今ここにいる」ことのリアル
「タイムマシンで過去は変更できるでしょうか?」
蒼井教授の研究室で、レンは時の彼方に想いを馳せることができます。
「過去も未来も、“現在”という意識から現実化されていく。戻りたい過去も、今この瞬間と融合し続けたんだ。」
「宇宙人は、なぜ僕らのそばに来ないんですか?」
「本当に“遠い存在”かな?」蒼井は机の上のクリスタル片を揺らしながら語る。
夜の静寂のなか、レンは協生館地下のプールを見つめている。
水面にる自分自身と向こうの時のこと。
すべての「現在」はフラクタルのように重なり合い、新たな物語を紡ぎながら。
最終章「境界を越えて――理論と意識の火中へ」
「教授、結局、物理と意識の関係って、どこまで説明できるでしょうか?」
「突破口があるかもしれない、それは自分を一切例外にせず――自分をも火の中に投入する覚悟で本質に向き合ってことだ。」
レンはアインシュタインの肖像を見上げる。
蒼井は静かに物思いにふける。
窓の外に広がる夕映えの光と、ほんの少し冷たくなった空気。
その中で、彼のまなざしは遠い過去と蒼いこれから向かう未来、そして自分の内側へと静かに向かう。
レンの問いかけや研究室の淡いざわめきも、いまは遠い背景音。
蒼井の頭の中は、現実と夢、意識と物理の謎が幾重にも渦を巻く。
思考の迷宮の奥底で、彼は自分自身すらも一つの観測者、果てしないフラクタル宇宙の小さなカケラに過ぎないと、気づく。
「まだ、すべてを知っていたわけじゃない。世界も、自分自身も……これからだ」
夜が明け、レンは優しい心の炎を灯す。
どんな天才の頭脳より、「自分自身を火の中に投げ込む勇気」こそが未来を切り拓く鍵だと確信する。
「……僕、もう一度初めから学び直してみます。」
蒼井教授は穏やかに微笑む。 その表情には、満足と新たな期待が滲んでいた。
静かな研究室を後にして、二人は夕暮れのキャンパスをゆっくり歩き出した。
歩みは軽やかで、確かに確かな決意に満ちていた。
未知という地平線の向こうで、どんな新しい発見が待っているのか――
レンと蒼井教授の探究は、再び動き始めたのだった。