- 心理カウンセリング教本【Kindle Book】
- うつ病アドバイザー無料資格問題集(WordPress)
- 「NPO全日本カウンセラー協会ブログ(アメブロ)
- 20世紀を代表する政治哲学者ハンナ・アーレントの『人間の条件』
- フェミニズム史における先駆女性思想家・文筆家スタール夫人(ジェルメーヌ・ド・スタール)
- Sign language.手話
- YUMI: The Digital Storyteller's Collection
- 黄昏のパートラムと渡良瀬の風
- 日本語の話し言葉における尊大表現と不適応
- 鬱病・躁病に通じる妄想を解消するアクションシステム
- 自殺念慮の理解と支援
- 自殺念慮の消し方〜うつ病と向き合うために〜
- 宇宙と共鳴する呼吸で鬱を祓うための音楽
- 星の巫女カウンセリングファイル《舞田みおの場合》
- 影の教室 ―ひまわり幼稚園事件ファイル―
- ジャスミンのコロンと路地裏のにおい──教室のカーストものがたり
- True Colors
- 『ドグラ・マグラ』『生殖記』で読み解く――“身体の声”に耳を澄ます精神鑑定の現在地
- 「どうにかなるでしょ ここの町のどこかで私は生きているのよ」
- 小豆に宿る呪術の力と「雨夜三人話」の悲劇
- Boulevard de la Mélancolie – Le repaire des jeunes dames
- Midaq Alley (زقاق المدق)
- 僕がどんなに君を好きか、君は知らない
- 隔(へだ)ての庭
- The boundary gate that is off-limits.
- 『神々の本性について』 Phaëthōn
- 「胎児の帰属」 ――胎内から始まる、血と記憶の犯罪。
- そして誰もいなくなった
- 消える夜 ―耳のない彼女―
- 幻夢の自己相似構造(フラクタルドリームスケープ)
- 日常と非日常の境界、日常生活のなかの人間心理の異質さを描く「Murder Mystery(マーダーミステリー)」
- 渇きの母胎(ぼたい)—水を求めて子を殺す—
- 最新ニュース速報
- Profiling Tarot.
- タロットリーディング
- 指示性のカウンセリング
- 鬱のお悩み相談
- NLP視線イメージ切り替え法
- 全日本カウンセラー協会
- 会社概要
NLP心理療法とロサンゼルス陪審評決 —— 売春婦殺人事件の謎をめぐって
NLP心理療法 VS 売春婦殺人事件陪審評決——コリン・クリステンセン事件の真相と法廷の心理戦
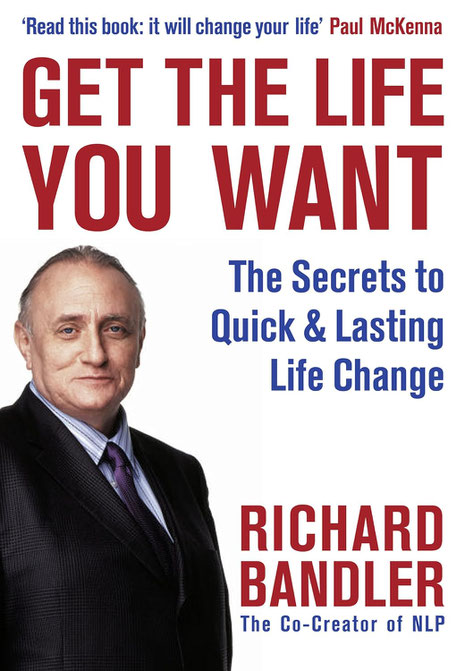
リチャード・バンドラー(Richard Bandler)
- アメリカの近代心理学セラピスト。
- 神経言語プログラミング(NLP)開発者
- 神経催眠再起パターン(NHR)システムを開発
- バンドラーは近代自己啓発運動の重要な人物
- ゲシュタルト療法のフリッツ・パールズのように話し、行動する。
言語学の変形文法で説明できるメタモデルと呼ばれるセラピーモデルを開発した。『魔術の構造 第1巻』(1975)
コリン・クリステンセン殺人事件
ロサンジェルスタイムズ 1988年1月29日 「サイコセラピスト無罪 — 売春婦殺人 — 陪審評決」
ロサンゼルスタイムズ1988年1月29日記事「Psychotherapist Not Guilty in Prostitute's Murder, Jury Finds」の要約:
- ニューラル・リンギスティック・プログラミング(NLP)の共同開発者であるリチャード・バンドラーは、売春婦コリン・クリステンセン殺害容疑で起訴されていた。
- 陪審員は5時間半の審議の末、バンドラーに対し無罪の評決を下した。
- 事件は、1986年11月にコリン・クリステンセンが射殺されたもので、バンドラーが加害者とされたが、彼は一貫して無実を主張。
- 裁判での焦点は、現場にいたもう一人の男ジェームズ・マリーノの証言の信憑性にあった。
- バンドラーは、クリステンセンを撃ったのはマリーノと証言。
- 陪審員は「合理的な疑い」が残るとし、有罪を支持するには証拠が不十分だと判断した。
- 陪審員のコメントでは、事件の詳細と証拠の一貫性の乏しさが無罪の要因になったと示唆された。
- この評決は社会的にも大きな注目を集め、NLP心理療法界や犯罪心理学関連領域でも波紋を広げた。
Is he truly innocent? Or did he use magic?
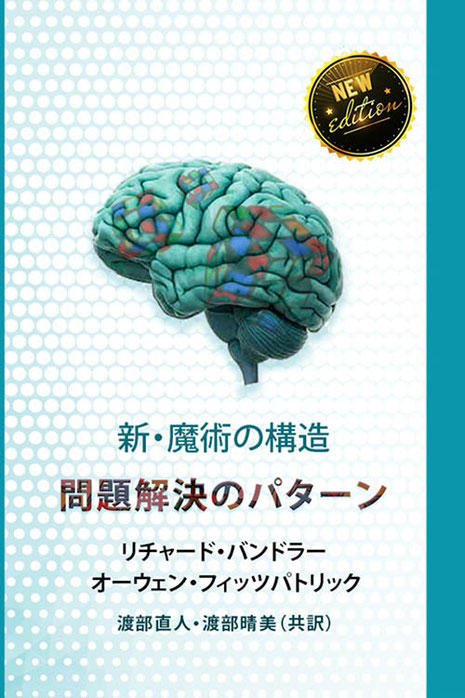
新・魔術の構造 問題解決のパターン
The New Structure of Magic-Patterns for Problem Solving
Richard Bandler (著), Owen Fitzpatrick (著), 渡部直人・渡部晴美(共訳)
1975年、リチャード・バンドラーのパイオニア的な著書「魔術の構造―The Structure of Magic」は、問題解決のための言語と心理学に関して、世界中の人々の思考に革命を起こしました。それから約50年の現在、この代表的な著作が全面的に改訂・更新され、現代社会で我々すべてが直面する問題へのアプローチ方法を再び変容させるような、さらに強力な洞察を提示しています。
Is he truly innocent? Or did he use magic?
リチャード・バンドラー(Richard Bandler)は、法的には無罪になりました。
裁判で「合理的な疑い(reasonable doubt)」が残るとして陪審員が無罪評決を下したため、法的には“無罪”が確定しました。
Is he truly innocent? Or did he use magic?
ただし“本当に無罪なのか?彼は魔法のトリックを使ったのか?”それは解明されていません。
- 司法上の無罪:
・バンドラーは売春婦コリン・クリステンセン殺人事件において、証拠不十分と証言の不一致を理由に、1988年1月のカリフォルニア州裁判所で陪審評決により無罪となりました。これは実際に法的な無罪判決(acquittal)です。
- 道義的・事実上の真実:
・裁判において無罪となった理由は、主な証人(事件現場にいた男ジェームズ・マリーノ)の証言の信用性に疑問があり、証拠がバンドラーの直接犯行を証明できなかったからです。
・「確実に潔白(完全な無実)」を直接証明した訳ではなく、「有罪とするだけの証拠がなかった」ための無罪です。
・真犯人や事件の全容については完全に解明されたわけではありません。
仮説及び推論
- 法的には「無罪」=犯罪行為は認定されていません。
- しかし、“本当に何も関与していないのか?”という真相は、証拠の不足・証言の矛盾が残るため、裁判所でも歴史的にも“本当の意味ではわからない”ままになっています。
これは「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法の原則を反映した裁判結果です。
リチャード・バンドラーは法律上は「潔白」として扱われています。リチャード・バンドラーは「法的には無罪」です。1988年のコリン・クリステンセン殺人事件に関する裁判で、陪審員は「合理的な疑いが残る」としながらも、有罪評決に至らず、無罪となりました。
裁判における「無罪」の意味
- 無罪は「事件に全く関与していない」という確定的事実を意味するのではなく、「有罪と断定できるだけの証拠が存在しなかった」ことを示します。
- 主な証人であるジェームズ・マリーノの証言の信頼性、証拠の不足、食い違う証言内容などが判決の根拠です。
- 法的には「無罪」=犯罪行為は認定されていません。
- 道義的・事実的「潔白」を完全に証明したわけではありませんが、「裁判所がバンドラーに有罪を認定できなかった」ため、無罪評決となっています。
Is he truly innocent? Or did he use magic?
すなわち、「本当に無罪か?」という問いには――
法で認定された無罪。真実(事実)の全容は裁判上明確にならず、今も“合理的な疑い”が残ったままです。
Is he truly innocent? Or did he use magic?
心理療法士リチャード・バンドラーがコリン・クリステンセンの死に関与したとされる事件は、水曜日遅くに陪審により審議された。評決はわずか5時間半の審議の後に示された。判決が読まれた際、バンドラーは法廷にいなかった。判決が出た後、彼の弁護士ゲリー・シュワルツバッハは記者団に語った。「彼(バンドラー)は犯罪を犯していないと証明された。評決の素早さが検察側の陳述の質を物語っている。」 この事件を起訴した地方検事補ゲーリー・フライは「驚きそして失望した」と述べた。
匿名を条件にある1人の陪審員は、バンドラーの罪には筋の通った疑いがある、と判断したと言った。
他の陪審員は評決に関するコメントを控えた。
検察の重要な証人はマリノだった。バンドラーとマリノは法廷で相反する証言をした。検察はバンドラーがクリステンセンを殺害したと主張。しかしバンドラーは、マリノがバンドラーの357口径マグナム銃でクリステンセンを殺したと証言した。
バンドラーの事件の予備審問の後、マリノは数ヶ月姿を消し、11月2日の裁判の開始時に出廷しなかった。
彼は逮捕状が発行された後、姿を現した。
父親不在による“ひきこもり”の性格プロファイリングと、NLP視線イメージ切り替え法
親子関係と“ひきこもり”の深層――神経言語プログラミング(NLP)で脳内イメージを変える視線ワーク
大人の経済社会の中で、利権といわれる「利益の独占」を確保するために「誰か」を不当に騙して「利権の関係者」以外を排斥するという「不当な不利益」を背負わせる暴力があります。これは、利益を要求する交渉の能力が遅れているという問題です。
現代社会の「利権構造」に潜む本質的な問題――「利益の独占」や、利権関係者による排他的な権益防衛、そのための情報操作や排斥・抑圧(“見えにくい暴力”)――このような構造では、利権グループが「利益のパイ」を囲い込み、一般の人や新規参入者、社会的に立場の弱い人たちが意図的に排除される状況が生まれます。
この排斥が、物理的な暴力ではなく、情報や権力、組織的なネットワーク、社会的評価を使ってなされる点に特徴があります。
「利益交渉能力の遅れ」とは何か?
- 利権関係の“内側”にいる人たちは、利害調整・交渉、影響力強化、ネットワークの支配を習慣的に行っています。
- 一方“外側”にいる一般人・異分野プレイヤー・若手・異文化層などは「交渉の経験値」「利害主張や論理展開」「自己利益と社会調和のバランス感覚」等々が、育成されにくい。
- そのため“利権システム”の枠外に立つ人は「自己利益を主張する術」や「参加条件・情報へのアクセス」において不利になりやすいです。
- この「交渉能力や社会リテラシーの“発達格差”」が、利権による排除=“社会的不当不利益”を構造的に助長しています。
この状況の本質的な暴力性
- 形式的には合法/社会秩序の一部に見えるが、本質的には「公平性」「社会的包摂」を脅かす排除的抑圧。
- 排斥の手法は、情報の囲い込み、不透明なルール設定、根回し、誹謗中傷、評価操作、人脈重視の不採用・昇進排除…など「見えにくい暴力」となって現れます。この社会問題の根幹には、「利権」を囲い込む側と排除される側の交渉能力・社会的交渉の“発達格差”があり、不当に背負わされる不利益と、その暴力性は“見えにくい”形で現代社会の随所に存在します。
集団の中でも個人であり続けるための父親からの学び
しかし、この問題の本質には「集団の中でも個人であり続ける」という概念・態度が十分に学習されていない、という現代社会の深い“病理”があります。
集団の中でも個人であり続ける――「個と集団」のバランス不全
日本を含め多くの社会では、「集団=安定・安心」「個=わがまま・異端視」といった文化的バイアスや同調圧力が根強く残っています。その結果、“集団の中”では自分の考えや個性を抑え、「集団の論理」「既存のルール」「利害関係」に無批判に従いやすくなる傾向があります。「一人ひとりが“大人としての個”の立場や意思を持つ」発達が阻害され、「出る杭は打たれる」的なメンタリティすら常態化しやすい。
「個を学ぶ機会の喪失」がもたらす病理
「個を学ぶ機会の喪失」がもたらす病理
家庭・学校・企業・社会全体のどの場面でも、「集団のメンバーシップ」ばかりが尊重され、「個人でいる勇気・責任・自律」の教育や実践が後回しにされがちです。
ひとりの“個”として発言する習慣、異議申し立てや自己表現、自己決定の経験が圧倒的に少なく、自分の考えを持つこと自体が不安・罪悪感につながる場合も多い。
結果として、既存集団の論理に巻き込まれ、「誰かを不当に排除する」「理不尽だと思っても従う」「集団の利益のためなら個人の犠牲も致し方ない…」といった病理現象が容易に生じます。
「集団」の中で埋没せず、「個人」として考え続ける姿勢が養われていないこと…これが“排除と不利益”構造の本当の病理です。
妄想を断ち切り「社会の中で個人を回復」するための視線イメージ切り替え法レッスン

「自分が社会の中で“個人”として生き直すには、“妄想”や自己否定の思考ループを断つ視線イメージトレーニングが役立ちます」
「妄想を消して社会の中の“個人”を回復する」ために、誰でもすぐできる視線イメージ切り替え法。
レッスン1:右目を右下に向けるワーク
1. イスに座ったまま、静かに目を閉じるか斜め下を向く。
2. 右目だけを意識して“右下”方向にそっと向ける。
3. この状態で「息が止まっている」「我慢している」「自分を責めている」自分自身の姿を、頭の中で思い浮かべる。
4. あえて少し苦しい感情・我慢や自責のイメージを受け入れながら、その呼吸の“止まり感”を感じてみる。
5. 無呼吸の自分が「他人や社会からの視線」で押しつぶされているイメージにも注目する。
ポイント
- 呼吸が浅くなったり止まりそうになる瞬間に“気づく”ことが、自己回復への第一歩です。
- 「我慢」「息苦しさ」「自分を責める」感情を、意識的にイメージ化することで、無意識に抱える妄想・思い込みを客観視できます。
- このワークを通じて、“個人”としての自分を社会や他者の圧から切り離し、内なる自己に意識を戻す感覚を育てましょう。
