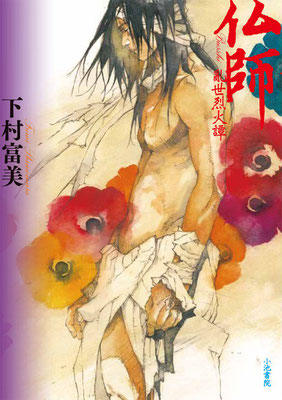- 心理カウンセリング教本【Kindle Book】
- うつ病アドバイザー無料資格問題集(WordPress)
- 「NPO全日本カウンセラー協会ブログ(アメブロ)
- 20世紀を代表する政治哲学者ハンナ・アーレントの『人間の条件』
- フェミニズム史における先駆女性思想家・文筆家スタール夫人(ジェルメーヌ・ド・スタール)
- Sign language.手話
- YUMI: The Digital Storyteller's Collection
- 黄昏のパートラムと渡良瀬の風
- 日本語の話し言葉における尊大表現と不適応
- 鬱病・躁病に通じる妄想を解消するアクションシステム
- 自殺念慮の理解と支援
- 自殺念慮の消し方〜うつ病と向き合うために〜
- 宇宙と共鳴する呼吸で鬱を祓うための音楽
- 星の巫女カウンセリングファイル《舞田みおの場合》
- 影の教室 ―ひまわり幼稚園事件ファイル―
- ジャスミンのコロンと路地裏のにおい──教室のカーストものがたり
- True Colors
- 『ドグラ・マグラ』『生殖記』で読み解く――“身体の声”に耳を澄ます精神鑑定の現在地
- 「どうにかなるでしょ ここの町のどこかで私は生きているのよ」
- 小豆に宿る呪術の力と「雨夜三人話」の悲劇
- Boulevard de la Mélancolie – Le repaire des jeunes dames
- Midaq Alley (زقاق المدق)
- 僕がどんなに君を好きか、君は知らない
- 隔(へだ)ての庭
- The boundary gate that is off-limits.
- 『神々の本性について』 Phaëthōn
- 「胎児の帰属」 ――胎内から始まる、血と記憶の犯罪。
- そして誰もいなくなった
- 消える夜 ―耳のない彼女―
- 幻夢の自己相似構造(フラクタルドリームスケープ)
- 日常と非日常の境界、日常生活のなかの人間心理の異質さを描く「Murder Mystery(マーダーミステリー)」
- 渇きの母胎(ぼたい)—水を求めて子を殺す—
- 最新ニュース速報
- Profiling Tarot.
- タロットリーディング
- 指示性のカウンセリング
- 鬱のお悩み相談
- NLP視線イメージ切り替え法
- 全日本カウンセラー協会
- 会社概要
- 黄昏のパートラムと渡良瀬の風
- 日本語の話し言葉における尊大表現と不適応
- 鬱病・躁病に通じる妄想を解消するアクションシステム
- 自殺念慮の理解と支援
- 自殺念慮の消し方〜うつ病と向き合うために〜
- 宇宙と共鳴する呼吸で鬱を祓うための音楽
- 星の巫女カウンセリングファイル《舞田みおの場合》
- 影の教室 ―ひまわり幼稚園事件ファイル―
- ジャスミンのコロンと路地裏のにおい──教室のカーストものがたり
- True Colors
- 『ドグラ・マグラ』『生殖記』で読み解く――“身体の声”に耳を澄ます精神鑑定の現在地
- 「どうにかなるでしょ ここの町のどこかで私は生きているのよ」
- 小豆に宿る呪術の力と「雨夜三人話」の悲劇
- Boulevard de la Mélancolie – Le repaire des jeunes dames
- Midaq Alley (زقاق المدق)
- 僕がどんなに君を好きか、君は知らない
- 隔(へだ)ての庭
- The boundary gate that is off-limits.
- 『神々の本性について』 Phaëthōn
- 「胎児の帰属」 ――胎内から始まる、血と記憶の犯罪。
- そして誰もいなくなった
- 消える夜 ―耳のない彼女―
- 幻夢の自己相似構造(フラクタルドリームスケープ)
- 日常と非日常の境界、日常生活のなかの人間心理の異質さを描く「Murder Mystery(マーダーミステリー)」
- 渇きの母胎(ぼたい)—水を求めて子を殺す—
小豆に宿る呪術の力と「雨夜三人話」の悲劇
YUMI: The Digital Tale Crafter
はじめに
日本の民間文化において、小豆は同一食材以上の意味を持っています。その赤い色は、伝統より呪術的な力を象徴し、厄除けや災厄払いの象徴とされてきました。
「雨夜三人話」の物語概要
「雨夜三人話」は、二つの家族の間での嫁の分岐を中心に展開される物語です。 舞台は、寝室あばら家や農村の生活が色鮮やかに描かれた時代の背景。
物語のクライマックスでは、フサが川底で溺死し、その口から小豆が三粒転がり出るという象徴的な描写が登場します。この小豆の存在が、物語全体に深い呪術的な意味を与えています。
柳田國男による小豆文化的意味
柳田國男は、小豆の「赤い色」に注目し、それが呪術力について多くの考察を残しています。 赤は古来より「魔除け」や「厄除け」の象徴とされ、特に小豆はその色と形状から、災厄を見せる力があると信じられてきました。
例、赤飯は祝い事に欠かせない料理ですが、これは単純な祝いの象徴ではなく、呪術的な見合いの意味を持つとされています。
物語における小豆の象徴性
「雨夜三人話」における小豆は、単体要素ではなく、物語の中で重要な象徴的な役割を果たしています。
呪術的な厄除けの象徴
フサの姑が米の上に小豆を三粒とした行為は、嫁に対する不信感や誤解の象徴として描かれています。
フサの死と小豆の関係
フサが溺死した際、口から小豆が三粒転がり出る描写は、彼女の死が突然事故ではなく、呪術的な力や出現の結果であることを暗示しています。
小豆が語る日本の民俗文化
「雨夜三人話」泣きながら描かれる小豆の象徴性は、日本の民俗文化における小豆の役割を深く反映しています。
「雨夜三人話」における小豆の描写は、物語の悲劇性を一層際立たせながら、日本の民俗文化における小豆の重要性を再認識させてくれます。
第1幕:伝統の重み
第1章:脆い均衡
フサコは、荒れ果てた屋根がほとんど藁葺きで覆われた故郷の家から嫁ぎ先に帰ってきた。義母のヨコは窓から彼女を見つめ、戻ってきた嫁の重荷についてつぶやいていた。フサコは黙って家に入り、非難の重さを感じた。彼女は夫のタツヤと共に、屋根裏から薪を下ろす手伝いをした。狭い空間で、二人の動きは慎重で息を合わせながら進んだ。フサコが簡単な食事の準備をする。彼女は米を量りながら手が震え、ヨコの批判的な視線を強く意識していた。
ヨコは黙って、フサコの後ろ姿を見つめていた。その背中がやけに細くなっていると思ったが、口に出すのはやめた。代わりに、火鉢の前で胡坐をかいて、古い新聞を丁寧に折り始めた。紙の擦れる音だけが室内に響く。夜はすぐそこまで迫っており、窓から入る風がわずかに焦げた藁の匂いを連れてきた。
「今日は…」フサコの声が、鍋と米と水の音に混じった。「玉ねぎで、味噌汁にします。大根は、明日まで残しときます」
「うちは玉ねぎが多い」と、ヨコは新聞紙の山から顔を上げた。
「多いけど、足りるまで刻んでしまいます」とフサコは言った。それ以上はとがめられることもなかった。包丁の音だけが続く。タツヤは一言も発さず、裏口の方で備蓄の薪をきちんと積み直している。働き者の男だが、肝心なときは何も言わない。フサコにはその沈黙が、ヨコの重く湿った咳払いよりも質が悪かった。
三人は遅い夕食を囲んだ。ちゃぶ台の足はがたついている。フサコは味噌汁をひと口すすり、両手を膝の上に揃える。ヨコは長い舌で歯に残った玉ねぎの繊維を舐
めるのだった。タツヤはといえば、箸を動かす以外に何ひとつ存在を主張しなかった。かすかに肩が揺れ、湯気の向こうで眼差しが一瞬だけフサコを捕らえる。だが、それだけだった。
食事が半ばを過ぎると、ヨコがふいに思い出したように声をあげた。「明日は町内の掃除じゃ。フサコ、あんたも出たらええ」
「はい」とフサコは即答した。玉ねぎの辛味で涙が滲んだ顔を、下を向いたままぬぐいもせずに。気配でタツヤがなにか言いかけたのを、ヨコがピシャリと睨み返して黙らせた。フサコは視界の端でタツヤの耳が赤くなるのを見て、うすら焦燥した。
できれば明日の掃除は誰かと交替してほしかったが、それは絶対言わないと決めていた。朝になれば、またヨコの圧力で「嫁の務め」を全うする。逃げられぬ縄のように、フサコの周にはりついていた。
その夜、タツヤは先に布団に潜り込んだ。天井の雨染みが月明りでぼうっと浮き上がるのを、彼はぼんやり眺めていた。かすかに畳の下が冷たい。フサコは居間で一人、家計簿の帳尻と格闘している。
灯油ランプの芯が赤々と燃えているが、机に落ちる光はかすかに揺れて、フサコの睫毛を不均等に照らし出した。帳簿の数字はどれも細かい字で、間違いが許されない。小銭一枚、米一合もごまかしはきかない。彼女の指先はこの家の家計をなんとか石橋のように支えていたが、それを感謝されることはほとんどなかった。紙の端に記された「四月分・味噌、米 二合分減額」の文字が、黒く滲んでいる。これでは夏まで持つかも怪しい。
彼女が書き物に没頭していると、障子の向こうからヨコの咳払いが聞こえた。
どこかためらうような息づかいだった。フサコはペンを置き、静かに障子を開け放つ。
ヨコは、半分ほどくたびれた背中を丸めて火鉢に向かっていた。「起きとるんか」と声をかけずとも、その気配でわかる。フサコは黙って茶を淹れ、そっとヨコの前に湯呑を置いた。ヨコはフサコの動きを、まるで虫でも見つめるような目で追った。黙って茶を一口すする。「あんた、よくやっとる」と言った。
それは、ヨコの口から出るには不自然な言葉だった。だが、フサコは返す言葉を持た
ていなかった。「ありがとうございます」とだけ絞り出すと、すぐにまた黙った。世間話の一つも出てこない。手元の湯呑が熱い。しばらくの沈黙のあと、ヨコが小さく笑った。「アンタら夫婦は、昔のわしとジイサンそっくりじゃ」「そうなんですか」
フサコは、話の先に何があるのか計りかねていた。ヨコの顔に真意が見えない。「そや。毎日くたびれとるような顔しよって。けど、それでええんじゃ」ヨコは一拍おく。「アンタは、丈夫なほうや。次の子できたら、もうちょっと楽になるかもしれん」
フサコの胸がざわつく。話がそこまでいくとは思っていなかった。ヨコは面倒くさそうに火鉢の灰をいじりながら、なぜかその先を言わなかった。けむりが帯のように天井へと立ちのぼる。
「……もう赤子はええやろ」フサコは喉の奥で呟いた。消え入りそうな声だった。
ヨコは耳が遠いふりをした。「昔はなあ、年に一度は必ずどこかで命の芽が出たもんじゃ。今のもんは堪え性がないんとちゃうかと、時々思うんよ」
フサコは、こめかみのあたりがジクリと痛んだ。自分の体の奥で、芽吹かなかったものの重みだけが残っている気が
した。つい最近まで、自分の腹に何かが宿ることはなかった。生まれては消える希望の層が、じっとりと冷たい腹膜に貼りつく。
「明日早いでな」ヨコはもう話すことがないらしく、茶を飲み干し、背中を向けた。フサコはよろめくような足取りで帳簿に戻ったが、もはや数字は焦点を結ばなかった。夜じゅう、米と金の勘定をつくろいながら、ヨコの言葉がまるで釘のように脳裏に残った。
午前五時、東の空がうっすら明るみはじめる。軒先にはまだ霜が残り、空気は喉を刺すほど冷たい。
フサコは洗顔場の井戸へ向かった。庭の泥を踏むたび、薄氷の下からぼこぼこと水の音がした。井戸の端で手を洗うと、皮膚がピリピリと痛む。空の色は鉛のように重く、まるで一切の希望を吸い取るかのようであった。
外に出て初めて、フサコは向かいの畑にちらほらと人影が動き始めていることに気づいた。隣家のオバタケ婆が、よろよろと鍬を振るっていた。婆はフサコに気づき、誰もいない朝の空気にむけてあいさつを投げる。「おはよう、フサコ」声は割れて、霧
に混じった。フサコは、氷を砕くような笑みで応えた。「おはようございます」
「霜が強い年は、鍬の刃も持ち上がらんよ」と婆は力なく言った。その手がしびれているのか、ときどき柄を落としかけた。今では周囲の年寄りばかりが先に起きて、日が昇る前から畑をいじっている。フサコはそんな景色がふと異様に感じられた。みなどこか、ねじれた根で地面に縛りつけられている植物のようだった。
井戸端に戻ると、ヨコがすでに裏口で待っていた。首に手拭いをひっかけ、下駄を履いている。「は
よいか、フサコ」とヨコは短く言い、なにか改まった風情で肩を張っていた。フサコは「はい」とだけ返し、二人並んで庭から表道に出た。町内の掃除といっても、土手のゴミ拾いと用水の泥さらいくらいのものだったが、それが「嫁の義務」とされていた。ヨコは道端に並ぶ家々の袖垣を見比べるように歩き、つい鼻で笑った。どの家も貧しいくせに、朝だけはきちんとした顔をする。そんな見栄と格式ばかりの世界を、フサコはただ無言で歩いた。
すでに十人ほどの女たちが集まっていた。
「よく起きたな」と、ややしわがれた声でフサコを迎えた。ヨコはもう出発する気でいる。一歩外に踏み出すと、地面の固さと冷たさが全身に伝わるが、ふたりは何も言わなかった。今朝の掃除は町内会館の周り――ひと昔前の公民館が改装されてからは、庭周りの落ち葉やごみ拾いが主な仕事だった。誰もが参加を嫌がったが、こうして嫁二人だけが無言で並ぶのは、昔からの習わしの一部だった。
町内会館までの道すがら、フサコの後を追うように、オバタケ婆もついてきた。道端には小さなゴミ袋が一か所にまとめて置かれている。フサコは拾い上げて中身を見た。去年のカレンダー、ちぎれた素麺の箱、湿った藁くず――どれもこの町の誰かが、目立たないように捨てたものだった。オバタケ婆が後ろから「それ、うちのかもしれん」と笑う。ヨコは「こんなもん、わざわざ町内で拾わせんでもええのに」と毒づいた。だが、そう言いながら真っ先にごみ袋を手にし、集積場まで黙々と運んだ。
フサコは、周囲の女たちの視線を感じていた。表情のない顔が並び、無言のまま手を動かしている。それぞれが家の前にいくつか点々と置かれているが、ほとんど空だった。朝の寒さがまだ残る路地で、彼女たちは落ち葉を掻き集め、紙くずやら割れた陶器の欠片やらを手早く拾い歩いた。町内の女たちが揃うと、声は小さいながらもそこに独特の温度が生まれた。噂話と忍び笑いが時折漏れる。だれそれの家の息子が就職に失敗した、こないだの葬式で誰が泣きすぎた、例のごとく取るに足らない話ばかりだった。だがそういう雑音が、朝の空気のかたさをやわらかくしていった。